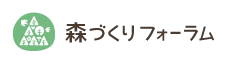夜遅く犬の遠吠えを聴くと、私はときどき庭に出てみる。この時間、私の上野村の家は明るい星空に照らされ、周囲を暗い山並みが囲んでいる。
その暗い山並みから、犬の遠吠えが聴こえることがある。私はそんなとき、その声がオオカミのものであることを期待している。といっても状況証拠は明らかに不利だ。オオカミに殺された動物の死骸も、オオカミのフンも、はるかに以前からみつかってはいないのだから。
記録によると、オオカミは、山村で焼き畑がさかんに行われていた頃に多かったらしい。焼き畑は粗放農業だから、草を求めて夜になるとウサギやシカが集まる。作物を失敬しようとする動物たちもいる。この動物たちをめざして、キツネやオオカミが集まった。松山義雄によると、オオカミが姿を消していく時期は、日本の山村から焼き畑が消滅していく時期と重なっているのだという。
オオカミもまた、森と村人の営みが重なり合う世界で暮らしていたのである。だから、山から人の営みが消えていったのは打撃だった。ちょうど薪炭林の消滅が、昆虫などの小動物や草花を追いつめているように。
こんな現実を見ていると、私はかつての「村」とか「集落」の意味を回復しなければならない、という気持ちになってくる。かつては、「村」も「集落」も、人間の暮らす社会だけを意味してはいなかった。その周囲に展開する田畑や川、森をふくめて、人々は「村」、「集落」と呼んでいたのである。人間の空間と自然の空間は分離されることなく、ひとつの時空のなかでとらえられていた。
とすると、オオカミは村の動物だったことになる。彼らは里に降りて送りオオカミとなり、夜の焼き畑を走り、村の自然のなかで暮らしていた。そして「村」が自然空間から切り離されて、人間の社会として認識されるようになったとき、すなわち自然の空間と人間の空間が分けてとらえられるようになったとき、自然と人間のすべての空間を「村」と呼んでいた時代の村の動物であるオオカミは、生きていけなくなった。森を自然としてとらえる視点のひろがりが、彼らを追いつめたのである。
「森林ボランティア」は、いま何を回復しようとしているのだろうか。出発点になっているものは、荒廃した森林の手入れであろう。しかしそこに、自然としての森林しかみることができなかったら、私たちはやはりオオカミが暮らした世界に敵対していることになる。私たちが本当に回復したいものは、オオカミを村の動物とみることができた時代の「村」であり、村の森ではなかったか。自然と人間が一体的にとらえられていた、あの時代の。
2002.01.05 森づくりフォーラム会報76号寄稿